大阪でオフィス移転・オフィスデザイン(内装)ならハタラクバデザイン
BLOG
オフィスデザインのレイアウト・内装工事に関するブログ
BCP対策とは?|概要・進め方から身近なオフィスでできる内容まで徹底解説
BCP(Business Continuity Plan/事業継続計画)は、災害などの非常事態に企業が円滑な運営を続けるために必要な備えです。今回はBCP対策の基本や重要な考え方について解説します。災害・事故などに対する備えは、企業の生命線を握る鍵です。オフィスで身近に取り組める実践的な内容も含め、いざという時に備えるためのステップを明確にしましょう。
目次
オフィスのBCP(事業継続計画)対策とは

BCPとは、Business Continuity Planの頭文字をとった言葉で、日本語では事業継続計画と呼ばれます。災害などの緊急事態が起きたときに事業を継続するため、企業があらかじめ計画を立てて備えておくことを意味します。BCPが求められる理由や、BCP対策を行ううえで重要な考え方について解説します。
BCP対策が求められる背景
近年、国内で地震・風水害などの自然災害が多発しています。それらの予測できない事態が発生した場合も自社の損害を最小限にし、ビジネスを継続できるよう備えるのがBCP対策です。自然災害に限らず、新型コロナウイルスのような疾患やサイバー攻撃による情報漏洩など、企業を取り巻く環境にはあらゆるリスクが潜んでいます。それらを未然に防ぐ手段を講じることで、企業の信頼性は高く保たれます。
BCP対策で重要なリスクアセスメントの考え方
リスクアセスメントとは、企業の中に潜む有害性や危険性を予測し、その除去や低減に努めることです。様々なリスクが事業継続性を阻害しないよう、以下の手順で計画を立てて対策を講じます。
・危険要因の特定、洗い出し
・危険性の重篤さや発生する可能性を含めてリスクの度合いを見積もる
・リスクの度合いに応じて優先度を設定
・それぞれのリスクに応じた低減措置の決定と記録
・定期的なリスクの見直しと優先度の修正
これにより、万が一緊急事態が発生した場合も事業の継続性を担保しながら、社員や顧客・取引先などへの深刻な被害を防ぐことにつながります。
BCP対策を実現に近づけるビジネスインパクト分析
ビジネスインパクト分析とは、自然災害などで業務やシステムが停止した場合の影響度を評価する手法です。事業が停止することによって考えられる被害の大きさ、影響の範囲を明らかにし、対応すべきリスクの優先順位付けに役立ちます。BCP対策を実効性の高いものにするには欠かせない分析手法です。
オフィスのBCP対策を行うメリット
オフィスのBCP対策を実施して得られるメリットは、主に3つです。
・取引先や顧客の信頼性が向上する
・社員が安心して働ける職場づくりにつながる
・会社全体の立て直しにかかる時間を短縮できる
それぞれ詳しくみていきましょう。
取引先や顧客の信頼性が向上する
BCP対策によって、万が一の事態が発生しても速やかに復旧できる体制を整えると、取引先・顧客・投資家から見て信頼性の向上につながります。復旧が早いということは、社外のステークホルダーへの損害も少ないことを意味するからです。そのため、BCP対策に関する取り組みは積極的に情報発信すると良いでしょう。
社員が安心して働ける職場づくりにつながる
日頃からBCP対策で緊急事態に備えることで、社員も「自社はきちんと対策を講じている」という安心感を持ちます。安心・安全は人間の欲求の中で基礎の部分であり、ここに不安を感じると会社自体への不信感にもつながりかねません。緊急事態の発生時に部署ごとでとるべき対策を決めておくと、それぞれの社員の役割が明確になって復旧への道筋がますます明らかにできます。
会社全体の立て直しにかかる時間を短縮できる
BCP対策を何もしていない場合、災害などの緊急事態が発生した際に事業の復旧が大きく遅れたり、最悪のケースでは廃業に追い込まれたりする可能性があります。そんな事態を避けるためにも、BCP対策で前もって商品・サービスの供給を復旧する方法を考えておきましょう。事業の立て直しでスムーズな初動対応ができれば、全体で見たときの復旧時間を短縮できるだけでなく、自社の損害も最小限に抑えられます。
BCP対策の進め方

BCP対策を役立つものとするためには、以下で解説する3つのステップが必要です。どれも重要なポイントなので、BCP対策の全体像を把握するためにぜひお役立てください。
STEP1:災害発生時の影響範囲を予測する
もしもの出来事が発生したとき、その影響の範囲を事前に予測するのは非常に重要です。どこにどのようなリスクが潜んでいるのかがわかれば、対策が立てやすいからです。自社が所有する資源を人材、資金、原料、データ、施設など大まかに分類し、それぞれに対して復旧の手段を考えます。特になくなっては困るものや復旧のボトルネックとなる資源については、日頃から代替手段を用意しておくとよいでしょう。
STEP2:目標設定をする
事業の継続に不可欠な業務(例えば、顧客サポート、ITシステムの維持など)を特定しておきましょう。
どの業務を、どのくらいの時間内に復旧させる必要があるかを明確にておくことが大切です。
STEP3:対策を策定する
業務が中断した場合にどのように対応するかを詳細に決定しましょう。
例えば、テレワークの導入、代替オフィスの設置、バックアップシステムの導入などです。
また、データバックアップ、サーバー、電源、通信手段などの物理的な設備やオフィスの設備(避難経路、非常用キットなど)を整備しておきましょう。
STEP4:復旧の優先順位と所要時間をシミュレーションする
緊急事態が起きた際に社内のどの事業を優先的に復旧するのか、またそれにかかる時間をシミュレーションします。優先順位付けには、自社の中でも売上比率が特に高い中核事業を軸に考えるとスムーズです。
・売上に貢献している事業はどれか
・自社の市場での評価やシェアを維持するために欠かせない事業はどれか
・取引先に大きな損害を与えてしまう事業はどれか
・自社が法的または財政的責務を満たすうえで不可欠な事業はどれか
これらのチェックポイントに沿って事業を棚卸しして、事業ごとに復旧の手順と必要な時間をあらかじめ把握しておくと安心です。
STEP5:事業継続計画の策定と共有
様々な分析によってまとめたBCP対策を文書化し、社内外のステークホルダーに共有します。特に社内では、社員に対してしっかり周知することが重要です。定期的に研修や勉強会を開催し、社員のBCP対策への意識が薄れないようにしましょう。また、計画は策定してそのまま運用するのではなく、自社を取り巻く状況の変化にあわせた見直しも忘れずに実施します。
また、災害時や非常時を想定した訓練を定期的に行い、実際の状況でも適切に対応できるようしておくことも大切です。
STEP6:BCPの意識を社内に広める
BCPの重要性を社員一人ひとりに理解してもらい、全員が協力して緊急時に迅速に対応できる体制を整えることが大切です。
経営陣や上層部から「BCPは全社的な課題であり、重要である」というメッセージを伝えてもらう、社内イベントなどを通じてBCPへの関心を高めることも有効です。
STEP7:見直しと改善
定期的にBCPを見直し、業務環境の変化や新たなリスクに対応できるように改善を行いましょう。
BCPは一度作成したら終わりではなく、企業環境や外部環境の変化に応じて柔軟に更新し、常に最適な状態を保つ必要があります。
BCP対策を意識したオフィス作りのポイント

BCP対策を行う際、オフィスでできることにはどういったものがあるのでしょうか。ここでは主に社内の身近なところで取り組むBCP対策についてお伝えします。
BCP対策を意識したオフィスビルの選び方
オフィスの建物自体の安全性もBCP対策には欠かせないチェックポイントです。以下の4つの視点で自社が入居する建物を今一度確認してみましょう。
・耐震性能の高さは十分か
・自家発電による電力供給システムの有無
・断水時の給水確保ができるかどうか
・自治体のハザードマップで災害リスクを確認
社屋自体を建て直すと膨大な費用がかかるため、設備の有無を事前に調べることは欠かせません。また、入居後もメンテナンスが必要なものについては必ず定期点検を受けましょう。
オフィス内で手軽にできるBCP対策
社員が働くオフィスの中でもBCP対策は不可欠です。
・耐震の備え(棚が倒れないように固定するなど)
・緊急時の避難経路を確保する(通路に荷物を置かない)
・災害備蓄品の定期的な購入とチェック
備蓄品は緊急事態が起きた際に社員がオフィスで過ごせるよう、日頃から買いそろえておく必要があります。一般的に、災害発生から72時間その場に滞在すると生命を守ることにつながると言われます。社内で安全に72時間を過ごすために、備蓄品の消費期限などは定期的にチェックしましょう。
社員へ災害時の行動について意識づけをする
BCP対策は計画を立てるだけではなく、社内にその重要性を波及させることも大事です。災害時にオフィスに起こり得るリスクの説明、避難訓練の実施、災害発生後にとるべき行動などをしっかり社員に周知しましょう。社内に共有する方法としては、講師を招いての研修会、ディスカッション、Eラーニングなど様々な手段があります。自社の環境にあわせて最適なものを選択してください。
オフィスBCP意識を社内に広めるための取り組み
1. 経営陣からのメッセージとリーダーシップ
トップダウンのアプローチ: 経営陣や上層部から「BCPは全社的な課題であり、重要である」というメッセージを強調することが、社員の意識を高める最も効果的な方法です。
経営陣がBCPの重要性を強調し、その優先度を明確に伝えることが必要です。
他企業のBCP対応事例や、自然災害、パンデミック等の影響を受けた実際の事例を共有することで、BCPの必要性を実感してもらうなどの方法も効果的です。
2. 教育とトレーニング
BCPについての基礎知識や具体的な行動指針を全社員に教育するプログラムを実施することでも意識を高められます。
避難訓練やシステム障害発生時の対応訓練など、実際にBCPを実行するシミュレーションを定期的に行い、社員がその重要性を体感できるようにすることで、BCPに対する理解を深めることも効果的です。
3. BCP担当者の選定と責任の明確化
BCPを推進するために、専任の担当者やチームを設置し、計画の進捗を管理しましょう。
社員それぞれに自分の役割や責任があることを明確に伝えることで、BCP発動時の具体的な行動指針を明示し、誰が何をすべきかを理解してもらいましょう。
4. 社内コミュニケーションの強化
BCPに関する情報を社内掲示板やイントラネットで随時更新し、誰でもアクセスできるようにしましょう。
また、BCPの進捗報告や新たな対策が決まった際に知らせるなど、BCPに関する情報や進捗状況を定期的にメールで送信し、社員に継続的に意識を促すことも効果的です。
5. 社内イベントやキャンペーンの実施
BCPに関連するクイズやパズルを社内で行い、楽しみながら学んでもらうなど、社内イベントやキャンペーンを通じてBCPへの関心を高めることも有効です。
BCPに関する週や日に特定のテーマを設定し、その期間にBCPの重要性を強調する活動を行うなどもよいでしょう。
6. フィードバックと改善の仕組み作り
BCPに関する意見や改善提案を社員から受け付ける仕組みを作り、社員自身がBCPの内容に関与していると実感してもらうことも大切です。
また、社員が気づいたリスクや問題点をフィードバックできる環境を作っておきましょう。
BCPを実際に適用した結果、スムーズに業務が継続できた成功事例を社内で共有し、BCPの効果を実感させることも大切です。
8. BCPの継続的な見直し
BCPの進捗や効果を定期的にレビューし、その結果を全社員にフィードバックしましょう。
また、状況の変化に応じて計画を見直し、最新の状態を保つことが重要です。
これらの取り組みを継続的に行うことで、オフィスBCPの意識が社内に浸透し、いざというときに全社員が協力して迅速に対応できる体制が整います。
オフィスのBCPの見直しが必要なタイミング
組織や業務の変更時
組織の構造変更、部門の統合・分割、従業員数の増減などがあった場合、それに伴いBCPの担当者や業務フローの変更が必要になります。
新しい業務内容や組織構造がBCPにどのように影響を与えるかを確認し、計画を最適化することで、非常時にも効果的に業務を継続できる体制を維持できます。
新しいリスクが発生した場合
地震や台風、パンデミック、サイバー攻撃など新たなリスクが発生した場合、既存のBCPがそれに対応しているか再評価する必要があります。
他にも、法律や規制が変わると、それに応じた対策を講じる必要があります。
BCPの実行結果や訓練後の改善点
定期訓練後の評価: 定期的に行うBCP訓練(避難訓練、ITシステムのバックアップテストなど)の結果を評価し、改善点が見つかった場合はすぐに計画を見直しましょう。
また、実際にBCPを発動するような事態が発生した場合、その結果を徹底的に振り返り、改善点を抽出して反映させましょう。
新たな技術やツールの導入
サーバーやネットワークの構成変更、クラウドサービスの導入、ソフトウェアのアップデートなどがあった場合、データのバックアップ方法やリモートワークの対応方法なども見直す必要があります。
社会的・環境的な変化
コロナ禍のように、リモートワークやテレワークが主流になる場合、オフィスBCPの見直しが不可欠です。
オンライン会議ツールやクラウドベースの作業環境への依存度が高まるため、その利用方法や緊急時の対応策をアップデートする必要があります。
まとめ
BCP対策は、事業の損害を最低限に抑えることはもちろん、働く社員を守るためにも重要な考え方です。今回解説したBCP対策の基礎をもとに、オフィスでの具体的な対策につなげていただければ幸いです。
「いきなり大きな計画を立てるのは難しい」という場合は、まず防災備蓄品をそろえるなど、身近なところから取り組んでみてはいかがでしょうか。黒田生々堂では企業に必要な防災備蓄品の販売や、期限管理のご相談もお受けしています。
お問い合わせ・お見積もりはこちら

ワークスタイルの関連記事

フリーアドレスを成功に導くための私物管理のポイント
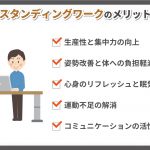
スタンディングワークとは?メリット・デメリットと効果的な導入方法を解説
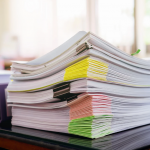
フリーアドレスの書類管理方法とは?利便性と安全性を両立するコツ
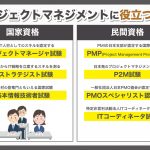
プロジェクトマネジメントに役立つ資格7選!取得するメリットも解説


サービスの流れ
ハタラクバデザインへのご依頼手順をご説明します。まずはお打ち合わせを行い、デザインプランのご提案を行います。ご不明な点があれば、お問い合わせフォームまたはお電話で、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ・無料御見積り





